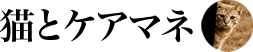学習内容に関する質問は、 こちらで受け付けています。
こちらで受け付けています。
このページ下部のフォームより、学習内容に関する質問の受付けをしています。ただし、回答のお約束はできません。可能なもののみ、回答させていただきます。また、回答には時間がかかる場合があります。無料での回答となるため、対応には限界があることをご理解いただければと思います。
質問と回答
| Y様より 2024年10月2日
>地域支援事業の財源について教えて下さい。
>介護予防・日常生活支援総合事業の財源構成に、第1号保険料23%・第2号保険料27%…となっていますが、H23年の問13の回答説明に、「地域支援事業支援納付金は第2号被保険者からの保険料で支払われている。」とあります。
>地域支援事業のうち、保険料で賄われるのは、総合事業は第1号・第2号、総合事業以外は第1号のみではないのでしょうか?
>私の理解が根本的に間違っているのかもしれません。ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
【回答】
まず、ご質問にある「『総合事業』の財源では、第1号保険料は23%、第2号保険料は27%」、「『総合事業以外』の財源では、第1号保険料はあるが(23%)、第2号保険料はない」という内容は適切です(2024ユーキャン速習レッスンP132、十訂基本テキスト上巻P153)。
また、「介護給付費・地域支援事業支援納付金は、第2号被保険者の保険料で賄われる」という内容も適切です(医療保険者は、徴収した第2号保険料を、支払基金に対して介護給付費・地域支援事業支援納付金として納付します。2024ユーキャン速習レッスンP133図・P135、十訂基本テキスト上巻P64図・P69)。
そして、支払基金は上記の納付金を、各市町村の特別会計に、介護給付費交付金と地域支援事業支援交付金として定率交付(27%)します。
このうち「地域支援事業支援交付金」は、「総合事業」の財源のみに使われます(「総合事業以外」の財源には使われません)。
ですので、「介護給付費・地域支援事業支援納付金は、第2号被保険者の保険料で賄われる」ということと、「『総合事業以外』の財源では、第1号保険料はあるが(23%)、第2号保険料はない」ということは矛盾しない、ということになります。
|
| E様より 2024年9月24日
>介護保険の第2号被保険者の自己負担割合が1割の理由がわかりません。
>テキストやインターネットで検索しても解答がみつかりません。
>よろしければ教えていただけないでしょうか。
【回答】
まず、介護保険法の第41条第4項や第48条第2項等において、介護保険の保険給付における利用者負担は、原則としてサービス費用の1割とされています。
これは、第1号被保険者と第2号被保険者のいずれかに限定して適用されるものではなく、両方に適用されるものです。
ただし、介護保険法の第42条の2と第59条の2において、一定以上の所得のある第1号被保険者の利用者負担は、2割または3割とされています。
以上のことから、第2号被保険者だけについて考えると、「第2号被保険者の利用者負担は1割」ということになります。
|
| T様より 2024年8月20日
>いつもお世話になります。スキマの時間に勉強するのに活用させてもらっております。下記について教えていただけるとありがたいです↓
>健康保険などの被用者保険では、支払基金への介護給付費・地域支援事業支援納付金は、加入者の報酬額に比例したもの(総報酬割)となっている。
>↑総報酬割が、よく分かりません。よろしくお願いします。
【回答】
第2号保険料における「総報酬割」の意義・仕組みについては、以下のQ&Aに詳しい説明がありますので参照してみてください。
 A 「総報酬割」は被用者保険(健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合など)での第2号被保険者個人の負担感を是正する仕組み
所得(報酬)に応じた負担感に
総報酬割について、以前の状況を踏まえながら以下に見てきます。
以前は個人の負担感に差があった
以前は、加入者の所得が多い医療保険者(主に大企業の健康保険組合など)や、加入者の所得が少ない医療保険者(中小企業の社員が加入する協会けんぽ)などに関係なく、各医療保険者は
「全国平均の第2号被保険者1人当たりの負担額×加入している第2号被保険者の人数」
という計算をして、人数に比例した金額を支払基金へ納めていました。
この仕組みだと、所得に対する保険料の割合が、大企業の健康保険組合などでは低く(個人の負担感が小さい)、協会けんぽでは高い(個人の負担感が大きい)、という状況となっていました。
総報酬割によって個人の負担感を是正
そこで導入されたのが、総報酬割です。これは健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合などの間で、それぞれの標準報酬総額に比例させて、それぞれが支払基金へ納める金額を決める、という仕組みです。
「標準報酬」とは、その医療保険の加入者の所得(報酬)の標準額です。これの加入者全員の合計が、「標準報酬総額」です。ですので、その医療保険の加入者の所得が多い場合は「標準報酬総額」も多くなり、所得が少ない場合は「標準報酬総額」も少なくなります。この「標準報酬総額」の多い・少ないに比例させて、健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合などそれぞれが支払基金へ納める金額を決めます。
たとえば、加入者の所得が多い健康保険組合では、支払基金へ納める金額が多くなります。逆に、加入者の所得が少ない健康保険組合では、支払基金へ納める金額も少なくなります。
このように、所得が多いところには多い金額を負担してもらい、所得が少ないところには少ない金額を負担してもらうことで、所得における保険料の割合を是正(個人の負担感を同じくらいに)しています。これが、総報酬割の仕組みです。
国民健康保険との関係
上記のように総報酬割は被用者保険(健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合など)の間での是正のために導入されたものであるため、国民健康保険は対象外とされています。
国民健康保険における2号保険料の場合は、所得階層や人数に応じて調整して算出されているので、前述の医療保険にあった収入における保険料の割合の格差は生まれません。
そして、第2号被保険者全員で負担する額を国民健康保険と被用者保険の間で人数に応じて分けたうえで、被用者保険に総報酬割が適用されて、国民健康保険も含めて第2号被保険者全員の負担感が同じくらいになるようになっています。
なお、当サイト内の「検索」も活用していただければと思います。
|
| S様より 2024年7月28日
>肺炎球菌ワクチンは定期接種の機会は一度だけとありますが他の問題では5年に一度となっていました。 何が違うのか教えてください。
【回答】
まず、「定期接種」というのは、「一定期間ごとに繰り返し接種する」という意味ではありません。「定められた時期に接種する」という意味です。
そして、高齢者の定期接種ワクチンである肺炎球菌ワクチンは、定期接種の機会は1回だけとされています。基本的には、65歳のときに接種することになっています。
※参考
以前は、65歳のときに接種できなかった人のために、「ワクチン未接種者は、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳のときにも接種できる」という経過措置がありました。こちらも、「5年ごとに繰り返し接種する」という意味ではなく、「接種できなかった場合は、5年後にまた機会が巡ってくる」という意味であり、接種の機会は1回のみです。
そして、この経過措置は令和5年度末で終了しています。
|
| U様より 2023年9月15日
>国保連は利用者等からの苦情処理の業務をしていますよね。 でも、その他の業務として、介護サービスの提供事業や介護保険施設の運営もしているんですよね。自分のところに来る苦情はどうするのですか。
【回答】
国保連が運営するサービス事業者・施設に対する苦情があった場合に、それを誰が処理するかについては、介護保険法では明確には規定されていません。ですので、これに関してケアマネジャー試験で問われるとは考えにくいかと思われます(試験は基本的に、法令に基づいた出題がされます)。
試験対策としては、国保連の業務の内容には、苦情処理や指定居宅サービスの事業などの運営がある、ということを学習していただければ良いかと思います。
なお、一般論としては、実際の現場において中立性や公平性に関する懸念もあることから、状況に応じて、市町村や都道府県が対応することも考えられます。
|
| T様より 2022年10月17日
>いつも拝見しています。ありがとうございます。介護サービス計画について、テキストやネットで調べてもわからないことが一つあり、そのことを質問をさせてください。
>
>居宅サービスを利用する際、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成した居宅サービス計画を元に、居宅サービス事業者で個別の計画(通所介護なら通所介護計画)を作成し、クライエントが施設入所した際は、在宅のケアマネジメントは終了となり、施設サービス計画のみになると思いますが、居宅サービスでも施設サービスでもなく地域密着型サービスのグループホームの場合の介護サービス計画はどうなるのでしょうか。小規模多機能型居宅介護の場合は、小規模多機能型居宅介護の介護支援専門員が居宅サービス計画と小規模多機能型居宅介護計画の両方を作成しますが、グループホームも同じく居宅サービス計画と認知症対応型共同生活介護計画の両方を作成するのでしょうか。それとも、施設入所の場合と同じように認知症対応型共同生活介護計画のみの介護サービス計画になるのでしょうか。ご回答よろしくお願いします。
【回答】
これは、ご質問の最後にある「認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)を利用する場合、施設入所の場合と同じように、認知症対応型共同生活介護計画のみになる」というお考えで適切です。
そもそも、居宅サービス計画を作成して、そこに位置づける必要があるのは、居宅サービス・地域密着型サービスのうち、区分支給限度基準額が定められているサービスを現物給付で利用する場合です。
居宅サービス計画を作成する大きな目的のひとつは、居宅の利用者が区分支給限度基準額の定められているサービスを組み合わせて現物給付で利用する際に、費用合計が上限を超えないよう管理することです。もし、区分支給限度基準額の定められているサービスを、計画しないまま現物給付で利用してしまうと、上限を超えてしまうことが容易に考えられるからです。つまり、区分支給限度基準額の定められているサービスを現物給付で利用する場合に、費用管理のために居宅サービス計画を作成して、そこに位置づける、ということです。
※このことは、介護予防サービス計画でも同様です。
こうしたことから、区分支給限度基準額が設定されているサービスについては、居宅サービス計画・介護予防サービス計画に位置づけることが現物給付の要件のひとつとされています(2022ユーキャン速習レッスンP73、九訂基本テキスト上巻P102)。
▼関連Q&A
居宅サービス計画に位置づける必要があるのは、居宅サービス・地域密着型サービスのうち、区分支給限度基準額が定められているサービスを現物給付で利用する場合です。
区分支給限度基準額の定められているサービスを現物給付で利用する場合に居宅サービス計画を作成する
居宅サービス計画を作成する大きな目的のひとつは、居宅の利用者が区分支給限度基準額の定められているサービスを組み合わせて現物給付で利用する際に、費用合計が上限を超えないよう管理することです。もし、区分支給限度基準額の定められているサービスを、計画しないまま現物給付で利用してしまうと、上限を超えてしまうことが容易に考えられるからです。つまり、区分支給限度基準額の定められているサービスを現物給付で利用する場合に、費用管理のために居宅サービス計画を作成して、そこに位置づける、ということです。
※このことは、介護予防サービス計画でも同様です。
こうしたことから、区分支給限度基準額が設定されているサービスについては、居宅サービス計画・介護予防サービス計画に位置づけることが現物給付の要件のひとつとされています(2021ユーキャン速習レッスンP73、九訂基本テキスト上巻P102)。
区分支給限度基準額が設定されていないサービスは、居宅サービス計画に位置づけなくてもよい
上記のような居宅サービス計画の意義からして、区分支給限度基準額が設定されていないサービスについては、居宅サービス計画への位置づけは不要となります。具体的には、個別に支給限度基準額が設定されている特定福祉用具販売と住宅改修、支給限度基準額が設定されていないサービスです(2021ユーキャン速習レッスンP83・P84、九訂基本テキスト上巻P九訂基本テキスト上巻P98~P100)。
※区分支給限度基準額の定められているサービスを現物給付で利用して居宅サービス計画を作成していて、特定福祉用具販売も利用する場合は、特定福祉用具販売についても居宅サービス計画に記入します(2021ユーキャン速習レッスンP157、九訂基本テキスト上巻P331)。
▼関連Q&A
https://caremane.site/48
▼区分支給限度基準額が設定されているサービス種類は、以下の「ポイント解説」を参照
区分支給限度基準・福祉用具購入費支給限度基準額・住宅改修費支給限度基準額について、◯か×で答えなさい
Q1 薬剤師による居宅療...
しかし、認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)には、支給限度基準額は設定されていません。そのため、居宅サービス計画の作成は不要となります。そして、認知症対応型共同生活介護計画のみを作成します。
※認知症対応型共同生活介護の“短期利用”の場合は、区分支給限度基準額が設定されているので、居宅サービス計画を作成する必要があります。
ちなみに、認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)と同様に、特定施設入居者生活介護と地域密着型特定施設入居者生活介護にも支給限度基準額が設定されていないので、居宅サービス計画の作成は不要となります。それぞれ、特定施設サービス計画、地域密着型特定施設サービス計画のみを作成します。
▼関連Q&A
支給限度基準額が設定されないサービスは、他の代替サービスがなく、他のサービスとの組み合わせは前提としていません。また、介護報酬の給付額が自動的に決まってきます(上限なく利用できるわけではありません。詳細は後述)。そのため、支給限度基準額を定める必要がありません。
支給限度基準額が設定されないサービス
|
●(介護予防)居宅療養管理指導
●居宅介護支援
●介護予防支援
●特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)
●介護予防特定施設入居者生活介護
●(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
●地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)
●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
●施設サービス(介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス)
※介護予防特定施設入居者生活介護には、そもそも「短期利用」はない。そのため「短期利用を除く」という記載もない。
|
それから、ご質問の前半にある理解は適切です。
通所介護や小規模多機能型居宅介護を利用する場合、これらには区分支給限度基準額が設定されているので、居宅サービス計画を作成する必要があります。
介護保険施設に入所して施設サービスを利用する場合は、施設サービス計画のみを作成します(施設サービスには支給限度基準額は設定されていないので、居宅サービス計画の作成は不要です)。
|
| T様より 2022年10月2日
>いつも大変参考にさせて頂いております。
>某問題集に出題されていた問題で、どうしても分からない箇所がありましたので質問させて頂きます。
>
>問題:介護保険法に規定する、都道府県介護保険事業支援計画で定めるべき事項、または定めるよう努める事項について。
>・各年度の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込み量確保のための方策。
>解答×
>
>これが何故誤りなのかが分かりません。
>市町村介護保険事業計画でも、介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みは策定すると解釈していましたが、分からないので解説を宜しくお願いします。
【回答】
まず、市町村介護保険事業計画と都道府県介護保険事業支援計画のどちらの「定めるべき事項」でも、「各年度の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み」を定めます(2022ユーキャン速習レッスンP129・130)。この点はご理解されているとおりです。
ただし、上記の設問で問うているのは、このことについてではありません。
設問を理解するポイントは、設問の最後にある「…確保のための方策」という部分です。この「確保のための方策」は、市町村介護保険事業計画の「定めるよう努める事項」にあるものです。
しかし、都道府県介護保険事業支援計画の「定めるべき事項」と「定めるよう努める事項」にはありません。そのため、解答×になります。
なお、この解釈は当サイト独自のものです。そのため、正確を期すなら、問題集の出版元に直接問い合わせるのが良いかと思います。
|
| T様より 2022年9月28日
>いつもお世話になっております。
>定期巡回随時対応型訪問介護看護は、市町村が介護報酬を独自に決められる。とテキストに記載がありましたが、どういう意味でしょうか?
>厚生労働大臣が単位数は決めて、どのサービスも一律であると記憶しています。地域密着型サービスは、市町村が独自に単位数を決めたりできるということなのでしょうか?
>ご回答いただけましたら幸いです。
>よろしくお願い致しますm(_ _)m
【回答】
まず、ご質問にある「厚生労働大臣が単位数を定めて、どのサービスでも単位数は全国一律である」という理解は適切です。
ただし、市町村は独自に、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護について、介護報酬の加算を設定できるとされています(市町村独自加算)。
この加算の設定するために、市町村は、事業者の指定基準の内容を上回る要件を定める必要があります。たとえば、市町村が独自に定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員基準を通常よりも厳しく定める、といったことです。これにより、サービスの質が高まります。
つまり、市町村が独自に指定基準を通常よりも厳しく定めて、これを満たして指定を受けた(サービスの質が高い)事業者は、加算を算定することできる、ということです。この「サービスの質の向上」が、市町村独自の介護報酬の目的のひとつです。
さらに、事業者にとっては、加算が算定できれば収入が多くなるので、これが事業への参入を促すことにも繋がります。
なお、この加算の単位数は、市町村が完全に自由に決められるわけではありません。これについて、厚生労働大臣が定める基準があります。
たとえば、定期巡回・随時対応型訪問介護看護では、厚生労働大臣が定める基準が「1か月につき50の倍数であって500を超えない単位数」とされているので、この基準に沿って市町村が設定します(ですので、たとえば市町村が定期巡回・随時対応型訪問介護看護の「市町村独自加算」として600単位を設定する、というのは不可です)。
※この厚生労働大臣が定める基準は、以下の「厚生労働大臣が定める地域密着型サービス費の額の限度に関する基準」になります。
厚生労働大臣が定める地域密着型サービス費の額の限度に関する基準
|
| H様より 2022年9月22日
>いつも試験勉強で頭が痛くなった時の気分転換にお世話になっております。
>質問なのですが23回の保健医療サービスの問題で訪問介護に関する問題があります。それに対する疑問なのですが
>
>介護支援専門員は、一定回数以上の生活援助中心型の訪問介護を、居宅サービス計画に位置付ける場合には、その居宅サービス計画を市町村に届けなければならない。
>
>→→訪問介護サービスは居宅サービスであり、居宅サービスの指定・監督は都道府県であるのに計画を届けるのは市町村なのは何故?? という疑問があります。訪問介護に限ったことではありませんが、
【回答】
訪問介護の「生活援助中心型」を一定回数以上、居宅サービス計画に位置付ける場合に、市町村に届け出るのは、市町村が保険給付を行う“保険者”だからです(指定・監督をするのが都道府県か市町村かは、直接関係しません)。
介護保険は基本的に、利用者に介護や機能訓練などのサービスを利用してもらうための制度です。
ただし、訪問介護の「生活援助中心型」のサービス内容は、掃除、洗濯、買い物、調理などの家事です(2022ユーキャン速習レッスンP356)。もちろん、それが必要となるケースもありますが、そればかりになってしまうと介護保険の基本的な目的には沿いません。
こうしたことを考慮し、「生活援助中心型」の不必要な利用をなくすために、厚生労働大臣が基準となる回数を設定して、それより多くなる場合には市町村に届け出ることとされています(2022ユーキャン速習レッスンP156)。
そして、市町村は該当の居宅サービス計画を検証して、「必要以上である」と判断がされれば、回数が減らされることがあります。
これは、保険給付の額を制限するということですので、保険給付を行う“保険者”である市町村が担当するのが適切であると言えます。
※ちなみに、訪問介護の「生活援助中心型」については、利用する時点で(訪問回数が少なくても)居宅サービス計画に、必要な理由(「一人暮らし」など)を記入することになっています。この必要な理由を記入する欄として、「居宅サービス計画書(1)」の「生活援助中心型の算定理由」欄があります(下記の資料を参照)。
居宅サービス計画書標準様式及び記載要領(PDF)
※参考
訪問介護の生活援助中心型についての「基準(厚生労働省の定める回数)」は、具体的には次のようになっています(こうした数字が試験で問われるとは考えにくいため、参考として見てください)。
◎訪問介護の生活援助中心型についての、厚生労働大臣が定める回数(1か月あたり)
要介護1 27回
要介護2 34回
要介護3 43回
要介護4 38回
要介護5 31回
※参考
ちなみに、指定・監督をするのが都道府県か市町村かに関係なく、全てのサービスの運営基準において、次の場合には市町村に通知することが規定されています(2022ユーキャン速習レッスンP104表内「利用者に関する市町村への通知」)。
・正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態(要支援状態)の程度を増進させたとき。
・偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、または受けようとしたとき。
これは、被保険者の認定区分や保険給付に関する事柄なので、認定と保険給付を行う“保険者”である市町村に通知するのが適切であると言えます。
>指定・監督が都道府県でも虐待事例などは市町村に届けるケースの問題があるなど、時々、市町村と都道府県の管理の理解がごっちゃになることが多いです。
>どのように整理したら良いですか?
【回答】
高齢者虐待の防止に関しては、(介護保険法ではなく)「高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)において、市町村が責任主体であると位置づけられています(2022ユーキャン速習レッスンP441)。
そのため、高齢者虐待防止法において、高齢者虐待に関する通報先は“市町村”と規定されています。
|
| M様より 2022年9月20日
>いつも参考にさせて頂いております。サイトや参考書をいくら見ても分からなかったことがあるため、質問させていただきました。
>車いす昇降機は、福祉用具貸与または住宅改修の対象になりますでしょうか?
【回答】
これは、設置に工事が必要かどうかで違ってきます。
車いす昇降機は「移動用リフト」の段差解消機に該当し、設置に工事が不要なものであれば、福祉用具貸与の対象となって保険給付されます(2022ユーキャン速習レッスンP380)。
設置に工事が必要なものであれば、福祉用具貸与の対象とはなりません。また、本体も設置工事も、住宅改修の対象にはなりません(2022ユーキャン速習レッスンP385)。つまり、設置に工事が必要なものは保険給付の対象ではなく、全額が利用者負担になる、ということです。
>小規模多機能型居宅介護を利用する場合、居宅サービス計画はその事業所のケアマネが作成する。同時に訪問リハビリテーションや訪問看護なども利用する場合は、それらを居宅サービス計画に位置づける。小規模多機能型居宅介護計画も、その事業所のケアマネが作成する。つまり、同時に訪問リハビリテーションや訪問看護なども利用する場合にのみ居宅サービス計画を作成して、小規模多機能型居宅介護だけの利用の場合は小規模多機能型居宅介護計画のみの作成でよい、ということでしょうか?
【回答】
まず、ご質問の前半にある「小規模多機能型居宅介護を利用する場合、居宅サービス計画はその事業所のケアマネが作成する。同時に訪問リハビリテーションや訪問看護なども利用する場合は、それらを居宅サービス計画に位置づける。小規模多機能型居宅介護計画も、その事業所のケアマネが作成する」という内容は適切です。
しかし、後半の「同時に訪問リハビリテーションや訪問看護なども利用する場合にのみ居宅サービス計画を作成して、小規模多機能型居宅介護だけの利用の場合は小規模多機能型居宅介護計画のみの作成でよい」という内容は違っています。小規模多機能型居宅介護だけを利用する場合であっても、居宅サービス計画を作成します。
小規模多機能型居宅介護には、区分支給限度基準額が設定されています。そして、区分支給限度基準額が設定されているサービスについては、居宅サービス計画に位置づけることが現物給付の要件のひとつとされています(2022ユーキャン速習レッスンP73)。
そのため、小規模多機能型居宅介護だけの利用の場合でも、現物給付で利用するために、居宅サービス計画を作成することになります。
▼関連Q&A
居宅サービス計画に位置づける必要があるのは、居宅サービス・地域密着型サービスのうち、区分支給限度基準額が定められているサービスを現物給付で利用する場合です。
区分支給限度基準額の定められているサービスを現物給付で利用する場合に居宅サービス計画を作成する
居宅サービス計画を作成する大きな目的のひとつは、居宅の利用者が区分支給限度基準額の定められているサービスを組み合わせて現物給付で利用する際に、費用合計が上限を超えないよう管理することです。もし、区分支給限度基準額の定められているサービスを、計画しないまま現物給付で利用してしまうと、上限を超えてしまうことが容易に考えられるからです。つまり、区分支給限度基準額の定められているサービスを現物給付で利用する場合に、費用管理のために居宅サービス計画を作成して、そこに位置づける、ということです。
※このことは、介護予防サービス計画でも同様です。
こうしたことから、区分支給限度基準額が設定されているサービスについては、居宅サービス計画・介護予防サービス計画に位置づけることが現物給付の要件のひとつとされています(2021ユーキャン速習レッスンP73、九訂基本テキスト上巻P102)。
区分支給限度基準額が設定されていないサービスは、居宅サービス計画に位置づけなくてもよい
上記のような居宅サービス計画の意義からして、区分支給限度基準額が設定されていないサービスについては、居宅サービス計画への位置づけは不要となります。具体的には、個別に支給限度基準額が設定されている特定福祉用具販売と住宅改修、支給限度基準額が設定されていないサービスです(2021ユーキャン速習レッスンP83・P84、九訂基本テキスト上巻P九訂基本テキスト上巻P98~P100)。
※区分支給限度基準額の定められているサービスを現物給付で利用して居宅サービス計画を作成していて、特定福祉用具販売も利用する場合は、特定福祉用具販売についても居宅サービス計画に記入します(2021ユーキャン速習レッスンP157、九訂基本テキスト上巻P331)。
▼関連Q&A
https://caremane.site/48
>介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所は、介護保険での契約による場合と、老人福祉法での措置による場合で、利用者負担額は違いますか?
【回答】
ご質問にあるような場合、利用者負担額は違ってきます。
介護保険での契約による入所の場合、利用者負担は原則1割(一定以上の所得のある第1号被保険者は2割または3割)となります(2022ユーキャン速習レッスンP72)。
一方、老人福祉法での措置による入所の場合、利用者と家族の所得に応じて費用を負担することになります(応能負担。2022ユーキャン速習レッスンP22)。
ですので、利用者負担額が違ってくることになります。
▼関連Q&A
「応能負担」は、負担能力応じて費用を負担する
その人の負担能力(収入が多いか少ないか)に応じて、費用を負担する方式です。
老人福祉制度の利用者負担は、応能負担です。たとえば、10万円分のサービスを受けた場合の利用者負担の金額は、収入の多いAさんは1万円で、収入の少ないBさんは4,000円、というようになります。
「応益負担」は、受けた利益に応じて費用を負担する
受けたサービスの量(受けた利益)に応じて、費用を負担する方式です。
介護保険制度の利用者負担は、応益負担です。たとえば、利用者負担割合が1割の人の場合、利用者負担の金額は、5万円分のサービスを利用したら5,000円で、10万円分のサービスを利用したら1万円になります。
>訪問介護で、身体介護・生活援助と、通院等乗降介助のどちらかを算定するケースには、どんなものがありますか?
>よろしくお願い致しますm(_ _)m
【回答】
そもそも訪問介護の介護報酬は、「身体介護中心」、「生活援助中心」、「通院などのための乗車または降車の介助中心」の3つに区分されています(2022ユーキャン速習レッスンP358)。
ですので、身体介護だけを利用した場合は、「身体介護中心」を算定することになります。同様に、生活援助だけを利用した場合は「生活援助中心」を算定し、通院等乗降介助だけを利用した場合は「通院などのための乗車または降車の介助中心」を算定します。
このように、訪問介護のどのサービス内容を利用したかによって、どの区分で算定するかが決まります。そして、利用したサービス内容の介護報酬だけを算定します。
|

 こちらで受け付けています。
こちらで受け付けています。